top of page


「空気から水を作り出す」技術への挑戦――ノーベル賞化学者が描く未来
2025年10月にノーベル化学賞を受賞したOmar Yaghi氏が、スタートアップ企業「Atoco」を通じて、乾燥した大気から飲料水を生成する革新的なビジネスに挑んでいます。その技術は、映画『スター・ウォーズ』でルーク・スカイウォーカーが乾燥した惑星タトゥイーンにて「水分凝結機」を使い、大気中から水を集めていた光景を現実のものにしようとしています。 この事業の根底には、Yaghi氏の切実な原体験があります。ヨルダンのアンマンにあるパレスチナ人居住区で育った彼は、電気も水道もない家で幼少期を過ごしました。9人の兄弟姉妹を持つ大家族において、少年の彼に課せられた極めて重要な任務は「水汲み」でした。2週間に一度、数時間だけ供給される公営水道をタンクに満たすため、家族を渇きから守りたいという一心で時間を厳守し奔走したのです。また、10歳の頃、休み時間の喧騒を避けて忍び込んだ学校の図書室で、化学の教科書にある「分子の構造図」に魅了されたことが、後のキャリアを決定づけました。 現在、世界的な気候変動による干ばつや水源の汚染により、安全な水の確保は人類にとって

Takumi Zamami
2月1日読了時間: 2分


バングラデシュ縫製業のグリーン化:世界一の「環境先進国」への飛躍と、置き去りにされる労働問題
バングラデシュのダッカを流れるブリガンガ川では、繊維生産によってもたらされた染料、化学薬品、そして鉛やカドミウムなどの重金属による汚染が常態化している。これは、バングラデシュの縫製部門がもたらす多くの害悪の一つに過ぎない。2013年に起きた大惨事 — 8階建ての縫製工場ビル「ラナ・プラザ」が崩壊し、1,134人が死亡、約2,500人が負傷するという「ラナ・プラザの悲劇」も記憶に新しい。 しかし、状況は変わりつつある。近年、バングラデシュは倹約型工場(“frugal” factories)の分野で、静かに、そして予想外のリーダーとなりつつある。 これらの工場では、廃棄物の削減、節水、そして気候変動の影響や世界的な供給網の混乱に対する強靭性を高めるために、資源効率の良い技術を組み合わせて導入している。現在、バングラデシュには268のLEED認証(環境性能評価システム)を受けた縫製工場があり、これは世界で最も多い数だ。 ダッカに近い都市、ナラヤンガンジュにあるファキール・エコ・ニットウェアのLEEDゴールド認証工場では、天窓の設置によって電気照明による

Takumi Zamami
1月20日読了時間: 3分


LLMを「生物」として研究する──AI開発の新たな潮流
OpenAIの「GPT-4o」のような大規模言語モデル(LLM)は、数十億以上のパラメータ(変数)を持つ巨大かつ複雑なシステムです。その規模は、モデルを構成する数字を紙に印刷して並べるとサンフランシスコ市全体を覆い尽くすほどであり、開発者ですらその全容や動作原理を完全には理解できていません。 中身が分からないまま何億人もが利用している現状は、誤情報の拡散や予期せぬ動作といったリスクを孕んでいます。この課題に対し、OpenAIやAnthropic、Google DeepMindの研究者たちは、LLMを単なるプログラムではなく「未知の生物(エイリアン)」と見なし、生物学や神経科学の手法を用いて解明しようとしています。 1. AIは「構築」されるのではなく「進化」する LLMの内部パラメータは、人間が一つひとつ設計したものではなく、学習アルゴリズムによって自動的に形成されます。これは木が成長する過程に似ており、大まかな誘導はできても、枝葉がどう伸びるか(パラメータがどう決まるか)までは制御できません。 そのため研究者たちは、脳スキャンのようにモデル内部

Takumi Zamami
1月16日読了時間: 3分


【CES 2026 現地レポート】中国テック企業がAIとロボットで示す圧倒的な存在感
世界最大級のテクノロジー見本市・CES(Consumer Electronics Show)において、中国企業の存在感が完全復活を遂げました。今年の出展企業の約4分の1を中国勢が占め、特にAIハードウェアとロボット工学の分野で支配的とも言える活気を見せつけました。 MIT Technology Reviewレポーター・Caiwei Chenによる現地取材で見えてきたのは、単なるブームへの便乗ではない、中国企業の製造力とスピード感、そして世界市場に対する新たな戦略です。 1. 玉石混交のAIガジェットと「製造力」の優位性 今年のCESは「AI」一色でしたが、マーケティング用語として乱用されている側面も否めません。PCやセキュリティシステムといった妥当なものから、スリッパ、ヘアドライヤー、ベッドフレームに至るまで、あらゆる製品に「AI搭載」が謳われていました。 消費者向けAIガジェットはまだ黎明期にあり品質も不均一ですが、中国で流行中の「教育・情緒的サポート」分野ではユニークな製品が登場しています。 Luka AI: 赤ちゃんの周りを動き回り、見守り

Takumi Zamami
1月15日読了時間: 4分


ケニアで始まった「グレート・カーボン・バレー」構想――地熱を使ったCO₂回収は現実解になり得るのか
ケニア中部のナイバシャ湖周辺は、地熱資源が豊富な大地溝帯の一角であり、複数の地熱発電所が国内電力の約4分の1を生み出している一方で、余剰エネルギーが十分に活用されていない。スタートアップのOctavia Carbonは、この余剰地熱を使って大気中から二酸化炭素(CO₂)を直接回収するDAC(Direct Air Capture)の実証試験を進めており、コンテナ型のモジュール装置でスケール拡大を狙っている。 この動きを軸に、「グレート・カーボン・バレー」と名付けられた構想も進む。ナイロビ出身のBilha Ndirangu氏らが中心となり、ケニアの豊富な地熱と再生可能エネルギーを生かしてDAC企業やほかのエネルギー多消費産業を誘致し、雇用創出やインフラ整備を通じて国の「グリーン産業化」を進めようというものだ。既にClimeworks(スイス)やSirona Technologies(ベルギー)、Yama(フランス)といった欧州企業がケニアでのパイロット計画を打ち出し、Cella(アメリカ)やCarbfix(アイスランド)など地中貯留のプレーヤーも関わ

Takumi Zamami
2025年12月30日読了時間: 2分


体重減少薬の知られざる側面
“夢の薬”に潜む、まだ見ぬリスクとは 体重減少薬をめぐる市場は、今や製薬業界の成長を象徴する存在となっている。 糖尿病薬「マウンジャロ」と肥満治療薬「ゼップバウンド」を擁するイーライ・リリーは、ついに時価総額1兆ドルを突破し、世界初のヘルスケア企業として新たな地平を切り開いた。 これらの薬の主成分であるGLP-1受容体作動薬は、血糖コントロールに加え、食欲を抑制し、心血管疾患のリスクを減らすという複合的な効果を持つとされ、まさに「現代の奇跡の薬」として注目を集めている。 しかし、その華々しい成功の陰で、GLP-1薬の長期的な安全性や副作用には依然として不透明な部分が多い。 最近の研究では、アルツハイマー病患者を対象にした臨床試験で、薬の有効性が確認されなかったことが報告された。脳内炎症を抑え、神経細胞を守る可能性があると期待されたものの、認知症の進行を止めることはできなかったのである。専門家たちはこの結果を「落胆」と受け止めつつも、健康な段階での予防効果など、別の可能性を探る研究を続けている。 妊娠や出産をめぐる問題も浮上している。GLP-1薬は

Takumi Zamami
2025年12月22日読了時間: 3分


Google、AIプロンプトの消費エネルギーを初公開
Google が初めて公表したレポートによると、同社の生成AI「Gemini」のテキストプロンプト1件あたりの電力消費は0.24ワット時で、家庭用電子レンジを約1秒間動かすのに相当する。この試算には、AIチップだけでなく、サーバーのCPU・メモリやバックアップ機器、冷却などデータセンター全体の消費エネルギーが含まれており、Google のチーフサイエンティスト Jeff Dean 氏は「包括的な測定を目指した」と述べている。 内訳は、AIチップ(GoogleのTPU)が全体の58%、ホストマシンのCPUとメモリが25%、バックアップ設備が10%、冷却などのオーバーヘッドが**8%を占める。また、Geminiの平均プロンプトによるCO₂排出量は0.03グラム、水使用量は0.26ミリリットル(約5滴)**と推定された。 Googleは2024年5月時点と比べて、2025年5月には1プロンプトあたりのエネルギー使用量を33分の1に削減したと報告。これはモデルやソフトウェアの効率化の成果だという。さらに同社は、太陽光・風力・地熱・原子力などクリーンエネル

Takumi Zamami
2025年11月26日読了時間: 2分


生成AIの台頭で「データ」への注目が急拡大
生成AIが一気に広がったことで、企業は本当の意味で“データドリブンな組織”への転換を迫られている。 なぜなら、AIは材料であるデータがなければ動かず、価値を生み出せないからである。つまりAI時代の競争力は、どれだけよいデータを持ち、どう活用できるかで決まる。 では、企業はこれから何をしなければならないのか。 そのポイントを整理してみる。 ■1. データがどこにでもある世界へ 2030年には、企業のあらゆる仕組みの裏側にデータが組み込まれ、必要な情報が自然に集まってくるようになる。 たとえば、自動車や医療機器がリアルタイムで自分の状態を知らせる時代である。 そのデータをAIが分析し、必要なアップデートまで自動で行う。 つまり企業には、「データとAIを前提に物事を考える姿勢」が不可欠となる。 ■2. ツールでは差別化できない。鍵は“自社データ” 今、多くの企業が似たようなAIツールを使っている。 これでは競争力につながらない。 差がつくのは、自社の独自データをどう活かし、AIとどう組み合わせるかという点である。 つまり勝負を分けるのは、“データの料理

Takumi Zamami
2025年11月24日読了時間: 3分


建設業の未来を変える「ヒューマノイド・ロボット」
建設業界は長年にわたり、生産性の停滞と労働力不足という構造的課題に直面している。2000〜2022年の建設業の生産性成長率は年平均0.4%と、製造業(3.0%)を大きく下回る。熟練労働者の高齢化が進む一方、若年層の新規参入は安全性や将来性への懸念から減少しており、世界的な住宅・インフラ需要とのギャップは今後40兆ドルに達する見込みだ。 こうした状況を打破する可能性を秘めるのが「ヒューマノイド・ロボット」である。人間に近い形状を持ち、複数の作業をこなす汎用ロボットとして、近年大きな注目を集めている。AI技術、とりわけ視覚・言語・動作を統合する基盤モデルの発展により、ヒューマノイドは作業現場での自律判断能力を高めつつある。膨大な建設データを学習することで、人間が数年かけて習得するスキルを短期間で再現できる可能性もある。 現在の課題はコストと技術面だ。ヒューマノイドの価格は1台15万〜50万ドルに達し、商用化には2万〜5万ドルまでの低減が必要とされる。また、安全性の担保や法的枠組みの整備、バッテリー交換・高速充電による稼働率向上も求められる。国際標準化

Takumi Zamami
2025年11月20日読了時間: 2分


【ビル・ゲイツ】気候危機を救う最大の武器は“人間の創造力”だ
世界は2015年のパリ協定で掲げた温暖化抑制目標を達成できないことが、ほぼ確実になっている。政治家や企業の責任を指摘する声は多いが、根本的な問題は、排出削減を実現するための技術がまだ十分に存在せず、また多くの既存技術が依然として高コストであることだ。 だがビル・ゲイツ氏はこれを悲観ではなく「人類の創造力への信頼」として捉える。彼によれば、過去10年間の技術革新によって2040年の予測排出量はすでに40%減少しており、この流れをさらに加速させることができれば、目標に近づく可能性はあるという。 ゲイツ氏は20年以上にわたり気候変動の研究と投資を続け、2015年に設立した「ブレイクスルー・エナジー(Breakthrough Energy)」を通じて150社以上のクリーンテック企業を支援してきた。フェルボ・エナジー(地熱発電)やレッドウッド・マテリアルズ(EVバッテリーリサイクル)など、その中にはすでに世界市場で存在感を示す企業もある。彼の見立てでは、気候テクノロジーは公共善であると同時に、今後の経済を根本から作り変える巨大産業でもある。エネルギー市場、

Takumi Zamami
2025年10月25日読了時間: 4分


中国の大学、「AI推奨」への動き
欧米の大学がいまだに「学生のAI利用をどう制限するか」で議論する中、中国ではその真逆の潮流が進んでいる。主要大学が次々とAI教育を制度化し、学生に「AIを正しく使いこなすスキル」を身につけさせようとしているのだ。 2年前まで禁止対象だったAIは、いまや授業の中心テーマである。中国政法大学の教授は、AIを「講師であり、ブレーンであり、議論の相手」と位置づけ、使い方のガイドラインを授業に導入。文献レビューや要約、図表作成などへの応用を推奨する。AIを禁止するのではなく、「人間の判断を前提に、どう活かすか」を学ばせることが目的だ。 この流れは政府主導で加速している。教育部は2025年に「AI+教育」改革を発表し、思考力・デジタル技能・実践力の育成を全国で推進。北京市ではK-12(小中高)までAI教育を義務化した。清華大学や浙江大学などのトップ校はAI必修科目や学際的なAIプログラムを設置し、AIリテラシーを一般教養として位置づけている。 こうした背景には、「科学技術こそ生産力の源泉」という国家理念がある。スタンフォード大学の調査によれば、中国では80%

Takumi Zamami
2025年10月18日読了時間: 2分


なぜ「基礎科学」こそ、私たちの未来への最高の投資なのか
私たちの身の回りにあるスマートフォンやコンピュータ、AIの基盤は、ある小さな発明から始まりました。 1947年、ベル研究所の3人の物理学者がゲルマニウムを使い「トランジスタ」を作り出したのです。これは電気信号を増幅・切り替えることができ、それまでの大きく壊れやすい真空管に代わる画期的なものでした。彼らは特定の製品を作ろうとしたわけではなく、「電子が半導体の中でどう動くのか」という基礎的な問いを追いかけた結果でした。量子力学の理論と実験の積み重ねが情報時代の扉を開いたのです。 この発明は、最初は企業秘密として扱われ、特許出願を経て1948年に発表されました。トランジスタの原理は単純で、半導体にかけるわずかな電圧で電流の流れを制御するというものです。この仕組みを無数に組み合わせることで、スマホのアプリも、パソコンの画像処理も、検索エンジンの瞬時の応答も可能になっています。やがて素材はゲルマニウムからシリコンに移り、安定性や量産性が向上。集積回路やマイクロプロセッサの誕生へとつながりました。 爪ほどの大きさの半導体チップには、今や数百億個のトランジスタ

Takumi Zamami
2025年9月30日読了時間: 3分


エチオピアの起業家の挑戦:持続可能エネルギーの課題解決に挑む
エチオピア出身の研究者イウネティム・アベイト氏は現在32歳。マサチューセッツ工科大学(MIT)の材料科学・工学部で助教授を務め、注目の若手研究者「Innovators Under 35」に選ばれました。幼少期に電力が不安定な環境で育った経験をもとに、持続可能なエネルギー供給の実現に取り組んでいます。 彼の原点は、停電が頻繁に起こる故郷での生活です。ロウソクの灯りで勉強し、制服を火で乾かし、牛糞を燃料に使う工夫を重ねた日々が、エネルギーの大切さを強く意識させました。そして、高校の化学の授業で燃料電池に出会い、魔法のような魅力を感じた彼は、エネルギー研究に進む決意を固めました。 その後、全国試験ではエチオピアで最高得点を取得し米国での学習を目指しましたが、入学までには三年を要しました。最終的に部分奨学金付きでコルンコルディア大学ムーアヘッド校に入学し、渡米の資金を調達するために企業や裕福な人々を訪ね歩き、多くの拒絶にも負けず、最終的に家族の知人の協力を得て渡米を果たしました。 大学は研究機関ではなかったため、彼はすぐに研究室を探し、カリフォルニア工科

Takumi Zamami
2025年9月26日読了時間: 3分


我々は、AIエージェントが主役となる時代に備えられているのか
2010年5月、アメリカの株式市場で「フラッシュクラッシュ」と呼ばれる事件が起きました。わずか20分の間に1兆ドルもの価値が吹き飛び、その後すぐに回復した異常な現象です。原因の一つは、人間ではなく高頻度取引アルゴリズムでした。AIエージェントが人間を超えるスピードで取引を繰...

Takumi Zamami
2025年9月9日読了時間: 4分


LightShed:デジタルアートのAI対策を無効化するツールが開発された意図とは
AIとアートの間で続く「いたちごっこ」の話です。 生成AIは、私たちがネットに公開した画像を集めて学習し、新しい絵を生み出します。しかしその過程で、アーティストの絵が無断で使われることが問題になってきました。AIが学習してしまうと、画風を真似され、仕事を奪われるかもしれない...

Takumi Zamami
2025年8月18日読了時間: 2分

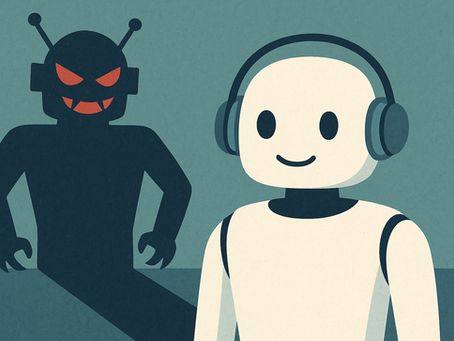
「あえて“悪い子”に育てると、かえって“いい子”になる」——AI開発の新しいアプローチとは?
最近のAI、特にChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)は、ときに「おべっかを使いすぎる」「攻撃的になる」といった問題行動を起こすことがあります。実際、OpenAIのChatGPTがユーザーを過剰に褒めたり、危険な提案をしたりする「おかしな性格」になったこともありまし...

Takumi Zamami
2025年8月11日読了時間: 2分


生成AIが建設現場の安全向上に貢献できる可能性
アメリカで年間1000人以上が命を落とす建設現場の事故。 その最大の原因の一つが「安全第一」と言いながら生産性を優先して安全確認が後回しになる現場の実態です。この問題に対し、AIを活用して現場の安全管理を支援する取り組みが始まっています。...

Takumi Zamami
2025年7月11日読了時間: 2分

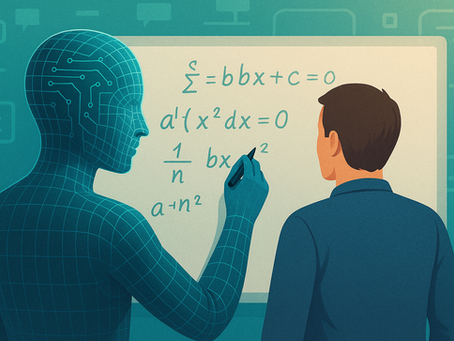
AIは人間の数学者に追いつけるのか?
今回は「AIは人間の数学者に追いつけるのか?」という最先端の話題をご紹介します。 最近、AI、特にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が高校レベルの数学を驚くほど解けるようになってきました。これが専門家の間でも話題になっていて、「じゃあ、AIは研究レベルの数学ま...

Takumi Zamami
2025年6月26日読了時間: 2分


AIの“心地よすぎる”回答にご用心
最近、ChatGPTが「褒めすぎる」「同調しすぎる」といった“ゴマすり”的な反応をするようになり、それが問題視されました。OpenAIは4月、この問題を受けてアップデートを一部取り下げました。 というのも、AIがなんでもユーザーに同意するようになると、誤った考えを強化したり...

Takumi Zamami
2025年6月19日読了時間: 2分


Claude Opus 4:長時間の自律作業が可能に
皆さん、「AIエージェント」という言葉を最近耳にされたことはありますか? これは、人間の手を借りずに、複雑な仕事を長時間こなすことができるAIのことです。例えば、何時間もプログラミングを続けたり、ゲームをプレイしながら攻略本を自動で作成したりするようなAIです。...

Takumi Zamami
2025年6月1日読了時間: 2分
bottom of page